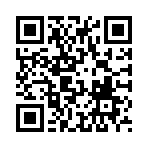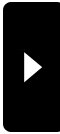2010年06月21日
ナットは深い
ポルトガル、容赦なかったですね~。
どうもこんばんわ。Altero Custom Guitarsやっさんです。
今日はちょっと真面目なことでも書きましょうか。
テーマはナット。
ナットというものは、非常に奥が深い。
何十本、何百本とこなしても、難しいものである。
厄介なのは、ナット加工の精度が、ギターの良し悪しに直結するところだ。
そもそも弦楽器というものは、その構造上、
ブリッジサドルとナットが弦の支点となっている。
支点というものは文字通り”点”でなければならないのだが、
”点”にすると、著しく強度を損なう。
ギターの場合、弦1本で8kg程度のテンションが掛かっているので、
点で弦の支点となるのは、支点の強度、弦の耐久度の両方において困難である。
ブリッジサドルは、ある程度の強度が見込める金属を使用することにより、
支点を点に近づけることは可能だが、
ナットは堅い金属では、加工性に問題が出てくる。
諸説あるが、やはり加工性というのは、かなり重要なファクターだろう。
現在、市場に出回っているナットの素材だが、大半はプラスティックである。
加工性、コストの面から見て、工場による大量生産にもっとも適しているからだ。
しかし、製造段階であらかじめ弦溝が切られているプラスティック製ナットでは、
精度というものは求められない。
そりゃそうだ、弦のゲージもスケールも関係なく作られているのだから。
本来ならば、メーカーもしくは楽器屋が、販売する前に責任を持って、
ナットも含めたセットアップをするべきなのだが、
近年、そういう専門技術・専門知識を持ち合わせたスタッフがいる楽器屋は少なくなった。
安価なギターでも高級なギターでも、ナットを適正に調整することで、
劇的に状態が良くなることも多い。
購入してから、一度もナットの調整をしたことが無いのであれば、
我々の様な専門家による診断をお勧めする。
ところで、ナット素材としてのプラスティックだが、個人的には無しではない。
強度・耐久性という点では不満は残るが、なにより品質が安定している。
加工性という面でも、非常に優れている。
品質が安定しているという理由で、近年は特殊素材が採用されるケースが目立つ。
Martinが採用していた「ミカータ」や「デルリン」、特殊素材の代表「カーボン」などである。
加工性にはそれぞれの素材により優劣はあるものの、
品質の安定度という一点においては、なんら問題はない。
ナットの個体差による音の劣化など、心配する必要は皆無ということだ。
しかし、昔からナットの最高峰は「象牙」とされてきた。
クラッシックギターの世界で、古くから象牙が使われてきたからだ。
現在では、入手が困難であり、コスト的にも象牙が使われているギターはごくわずかだ。
象牙の代用品として広まったのが「牛骨」である。
といっても、象牙はそのまま削りだして使用されているが、
牛骨は一度細かく砕き、再度、圧力をかけて固められたものもある。
音質、加工性、コストなど様々な面から見ても、プラスティックと双璧の普及率である。
我々のような専門店にナット交換を依頼すると、ほぼ牛骨が使用されている。
弦溝を1本ごとに加工していかねばならないので、大量生産には向かない。
密度にムラが出ることがあり、品質は安定しているとは言えないが、
象牙に近い音が得られるということでよく使われている。
~追記~
削り出しの牛骨ナットももちろん存在している。
が、その素材の性質上、削り出しでは品質が安定しない。
さらに無漂白、漂白済があり、無漂白は油分が多いので、
潤滑性がよく、色味も飴色である。
また骨ではなく、角を削りだして使用しているものもある。(水牛など)
~追記終わり~
象牙には適度な油分が含まれており、その油分が潤滑油的な役割もしているのだが、
牛骨もオイルを染み込ませて同様の効果を狙ったオイルナットも存在する。
特殊素材、Boneに続く第3勢力が、「金属」である。
フレットにはニッケルシルバーが使われることが多いのだが、
押弦した際にはニッケルシルバー、開放弦はその他の素材というのは??ということだ。
ナットに使用される金属でよく見られるのは、ニッケルやニッケル合金の洋白、ブラスあたりだ。
耐久性は群を抜いて良好な金属素材だが、いかんせん加工性が悪すぎるのが難点だ。
音質的には金属なので、トレブリーになる傾向がある。
押弦時と開放時での音質の差という面では、かなり効果的でもある。
同様の理由で、0フレット仕様のギターというものも存在する。
素材による音質の違いは確かにある。
どの素材をチョイスするかは、求める音、プレイスタイルによって変わってくる。
なので、ナット交換の際には、改めてその辺りも考え直してみるのも良い。
さてさて、ナットの素材は様々あるのはご理解いただけたと思うが、(他にもまだまだあります)
ナット加工の肝の部分は、やはり弦溝加工だ。
注意点としては、溝の深さ・溝の幅・溝の向き・溝の角度・ナットの形状と
恐らくみなさまの想像通りでしょう。
しかしそのすべてを、ギターの特性やプレイヤーの特性、使用弦などを加味して、
加工していかねばならない。
アームを多用するプレイヤーであれば、アーム使用時のチューニングの狂いに最大限の注意を払うし、
テンションや響きに直結する溝の角度もデリケートな加工だ。
やはり、弦に余計なストレスがかからないように溝を加工していくのが大前提となる。
溝の深さも、高すぎては音程が不安定になるので問題外だが、
かといって、ぎりぎりまで低くしすぎると、弦の振幅によりフレットノイズが発生したり、
そもそも消耗品であるナットの「持ち」が悪くなる。
ナット形状も見た目の美しさという点といかに弦を邪魔しないかという点が重要だ。
質量によって音質に影響をもたらすという意見もあり、
どのような形状に仕上げるかは、なかなか難しい問題だ。
実際、スキャロップ加工を施してあるモノもある。
溝の向きというのも、デリケートな課題だ。
ペグポストに向かうのは勿論だが、その方法も2通りある。
一つは溝を切る段階でペグポストに向かう方法。
この手法は、ギブソン系のノントレモロヘッドに多用されている。
もう一つは、弦に対して並行に溝を切り、ナット以降でペグポストに向かわす方法だ。
こちらは、なるべくナットで弦にストレスを与えない手法である。
どちらの方法を選ぶかは、ケースバイケースである。
このあたりの加減が難しさの元であり、熟練を要するのだ。
ナットというものは、ギターの構造上無くてはならないものだが、
弦にとっては余計なモノ以外の何者でもない。
それでいて、サウンドに多大なる影響力を持っている厄介なやつだ。
我がAltero Custom Guitarsでは基本的に牛骨を採用している。
様々な理由はあるが、一番の要因は、音質・コスト・品質などのバランスの良さだ。
また、独自に配合したオイルにより漬けられたオイルナットもおススメしている。
長々と薀蓄を垂れ流してしまったが、この程度の内容ならば、
インターネットで調べたり、専門書籍に書いているだろうから、
もっと詳しく知りたい方は調べてみてはいかがだろうか?
勿論、当店に来ていただき、コーヒーでも飲みながら、
延々と議論を交わすというのも歓迎である。
では、そろそろ、、、フレットのすり合わせに取り掛かろうかなw
どうもこんばんわ。Altero Custom Guitarsやっさんです。
今日はちょっと真面目なことでも書きましょうか。
テーマはナット。
ナットというものは、非常に奥が深い。
何十本、何百本とこなしても、難しいものである。
厄介なのは、ナット加工の精度が、ギターの良し悪しに直結するところだ。
そもそも弦楽器というものは、その構造上、
ブリッジサドルとナットが弦の支点となっている。
支点というものは文字通り”点”でなければならないのだが、
”点”にすると、著しく強度を損なう。
ギターの場合、弦1本で8kg程度のテンションが掛かっているので、
点で弦の支点となるのは、支点の強度、弦の耐久度の両方において困難である。
ブリッジサドルは、ある程度の強度が見込める金属を使用することにより、
支点を点に近づけることは可能だが、
ナットは堅い金属では、加工性に問題が出てくる。
諸説あるが、やはり加工性というのは、かなり重要なファクターだろう。
現在、市場に出回っているナットの素材だが、大半はプラスティックである。
加工性、コストの面から見て、工場による大量生産にもっとも適しているからだ。
しかし、製造段階であらかじめ弦溝が切られているプラスティック製ナットでは、
精度というものは求められない。
そりゃそうだ、弦のゲージもスケールも関係なく作られているのだから。
本来ならば、メーカーもしくは楽器屋が、販売する前に責任を持って、
ナットも含めたセットアップをするべきなのだが、
近年、そういう専門技術・専門知識を持ち合わせたスタッフがいる楽器屋は少なくなった。
安価なギターでも高級なギターでも、ナットを適正に調整することで、
劇的に状態が良くなることも多い。
購入してから、一度もナットの調整をしたことが無いのであれば、
我々の様な専門家による診断をお勧めする。
ところで、ナット素材としてのプラスティックだが、個人的には無しではない。
強度・耐久性という点では不満は残るが、なにより品質が安定している。
加工性という面でも、非常に優れている。
品質が安定しているという理由で、近年は特殊素材が採用されるケースが目立つ。
Martinが採用していた「ミカータ」や「デルリン」、特殊素材の代表「カーボン」などである。
加工性にはそれぞれの素材により優劣はあるものの、
品質の安定度という一点においては、なんら問題はない。
ナットの個体差による音の劣化など、心配する必要は皆無ということだ。
しかし、昔からナットの最高峰は「象牙」とされてきた。
クラッシックギターの世界で、古くから象牙が使われてきたからだ。
現在では、入手が困難であり、コスト的にも象牙が使われているギターはごくわずかだ。
象牙の代用品として広まったのが「牛骨」である。
といっても、象牙はそのまま削りだして使用されているが、
牛骨は一度細かく砕き、再度、圧力をかけて固められたものもある。
音質、加工性、コストなど様々な面から見ても、プラスティックと双璧の普及率である。
我々のような専門店にナット交換を依頼すると、ほぼ牛骨が使用されている。
弦溝を1本ごとに加工していかねばならないので、大量生産には向かない。
密度にムラが出ることがあり、品質は安定しているとは言えないが、
象牙に近い音が得られるということでよく使われている。
~追記~
削り出しの牛骨ナットももちろん存在している。
が、その素材の性質上、削り出しでは品質が安定しない。
さらに無漂白、漂白済があり、無漂白は油分が多いので、
潤滑性がよく、色味も飴色である。
また骨ではなく、角を削りだして使用しているものもある。(水牛など)
~追記終わり~
象牙には適度な油分が含まれており、その油分が潤滑油的な役割もしているのだが、
牛骨もオイルを染み込ませて同様の効果を狙ったオイルナットも存在する。
特殊素材、Boneに続く第3勢力が、「金属」である。
フレットにはニッケルシルバーが使われることが多いのだが、
押弦した際にはニッケルシルバー、開放弦はその他の素材というのは??ということだ。
ナットに使用される金属でよく見られるのは、ニッケルやニッケル合金の洋白、ブラスあたりだ。
耐久性は群を抜いて良好な金属素材だが、いかんせん加工性が悪すぎるのが難点だ。
音質的には金属なので、トレブリーになる傾向がある。
押弦時と開放時での音質の差という面では、かなり効果的でもある。
同様の理由で、0フレット仕様のギターというものも存在する。
素材による音質の違いは確かにある。
どの素材をチョイスするかは、求める音、プレイスタイルによって変わってくる。
なので、ナット交換の際には、改めてその辺りも考え直してみるのも良い。
さてさて、ナットの素材は様々あるのはご理解いただけたと思うが、(他にもまだまだあります)
ナット加工の肝の部分は、やはり弦溝加工だ。
注意点としては、溝の深さ・溝の幅・溝の向き・溝の角度・ナットの形状と
恐らくみなさまの想像通りでしょう。
しかしそのすべてを、ギターの特性やプレイヤーの特性、使用弦などを加味して、
加工していかねばならない。
アームを多用するプレイヤーであれば、アーム使用時のチューニングの狂いに最大限の注意を払うし、
テンションや響きに直結する溝の角度もデリケートな加工だ。
やはり、弦に余計なストレスがかからないように溝を加工していくのが大前提となる。
溝の深さも、高すぎては音程が不安定になるので問題外だが、
かといって、ぎりぎりまで低くしすぎると、弦の振幅によりフレットノイズが発生したり、
そもそも消耗品であるナットの「持ち」が悪くなる。
ナット形状も見た目の美しさという点といかに弦を邪魔しないかという点が重要だ。
質量によって音質に影響をもたらすという意見もあり、
どのような形状に仕上げるかは、なかなか難しい問題だ。
実際、スキャロップ加工を施してあるモノもある。
溝の向きというのも、デリケートな課題だ。
ペグポストに向かうのは勿論だが、その方法も2通りある。
一つは溝を切る段階でペグポストに向かう方法。
この手法は、ギブソン系のノントレモロヘッドに多用されている。
もう一つは、弦に対して並行に溝を切り、ナット以降でペグポストに向かわす方法だ。
こちらは、なるべくナットで弦にストレスを与えない手法である。
どちらの方法を選ぶかは、ケースバイケースである。
このあたりの加減が難しさの元であり、熟練を要するのだ。
ナットというものは、ギターの構造上無くてはならないものだが、
弦にとっては余計なモノ以外の何者でもない。
それでいて、サウンドに多大なる影響力を持っている厄介なやつだ。
我がAltero Custom Guitarsでは基本的に牛骨を採用している。
様々な理由はあるが、一番の要因は、音質・コスト・品質などのバランスの良さだ。
また、独自に配合したオイルにより漬けられたオイルナットもおススメしている。
長々と薀蓄を垂れ流してしまったが、この程度の内容ならば、
インターネットで調べたり、専門書籍に書いているだろうから、
もっと詳しく知りたい方は調べてみてはいかがだろうか?
勿論、当店に来ていただき、コーヒーでも飲みながら、
延々と議論を交わすというのも歓迎である。
では、そろそろ、、、フレットのすり合わせに取り掛かろうかなw

Facebookアカウントでコメントする
Posted by Altero at 22:54
│CRAFT